1年生:春学期編
Open Menu
 高校生、受験生、保護者の皆様、こんにちは。この度は、横浜国立大学 経営学部、並びにDSEPにご関心をお持ち頂き、ありがとうございます。私は経営学部DSEP運営委員長の鶴見裕之と申します。
高校生、受験生、保護者の皆様、こんにちは。この度は、横浜国立大学 経営学部、並びにDSEPにご関心をお持ち頂き、ありがとうございます。私は経営学部DSEP運営委員長の鶴見裕之と申します。このページでは、DSEP第1期生に志望動機や入学してからの感想などをインタビューした様子を高校生、受験生、保護者の皆様にお届けいたします。
インタビューは2021年7月28日に行われました。インタビューにご協力頂いたのは経営学部DSEP1年生の稲岡玲さん、廣田太一さんのおふたりです。インタビュアーは私、鶴見が務めました。

---2021年7月28日、横浜国立大学の経営学研究棟 応接室にて。
鶴見 2021年4月に、経営学部データサイエンス教育プログラム(通称:経営学部DSEP)が始動しました。春学期中も、毎週水曜日にDSEP1期生全員が常盤台キャンパスに集い、2人の教員の指導による「データサイエンス・ゼミナール」が開催されています。今日は、1期生のおふたりにお集まり頂き、経営学部DSEPに興味を持ったきっかけ、入学してみての感想、これから取り組んでみたいことについて、伺ってみたいと思います。
経営学部DSEPに興味を持ったきっかけ
鶴見 経営学部DSEPに関心を持ったきっかけを教えて下さい。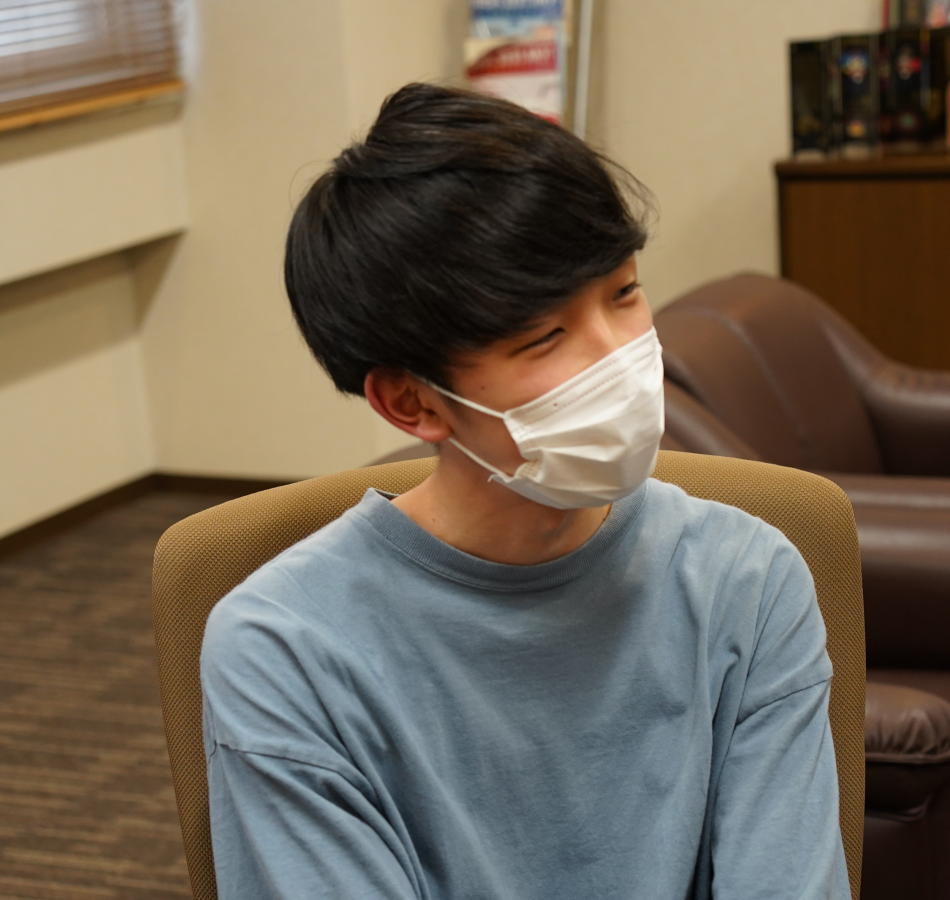 廣田さん 私は小さい頃から、数学が好きで、得意でした。その流れで、高校でも理系を選択しました。進路選択でも数学を活かし、大学では自然科学を学び、将来の仕事も自然科学を通じて、社会と関わり合う事をはじめはイメージしていました。
廣田さん 私は小さい頃から、数学が好きで、得意でした。その流れで、高校でも理系を選択しました。進路選択でも数学を活かし、大学では自然科学を学び、将来の仕事も自然科学を通じて、社会と関わり合う事をはじめはイメージしていました。しかし、考えを進めてゆく中で、最終的に社会との関わりを持つのであれば、もっと直接的に社会と関わりあえる仕事に就きたいと思う様になりました。その中でアクチュアリー*に興味を持ち、直接お話を伺ったりもしたのですが、自分としては、保険に特化するよりも、幅広く社会との接点を持ちうる仕事に就きたい、と次第に考える様になりました。
最終的に、数学を駆使して、活躍が出来、広く社会に貢献しうる仕事として、データサイエンスを自分の進路として選択しました。そして、企業経営とデータサイエンスの双方を学べる、横浜国立大学の経営学部DSEPを志願するに至りました。
*確率論・統計学などを用いて、将来のリスク等を分析する専門職。保険、年金、資産運用などの分野で活躍しています。
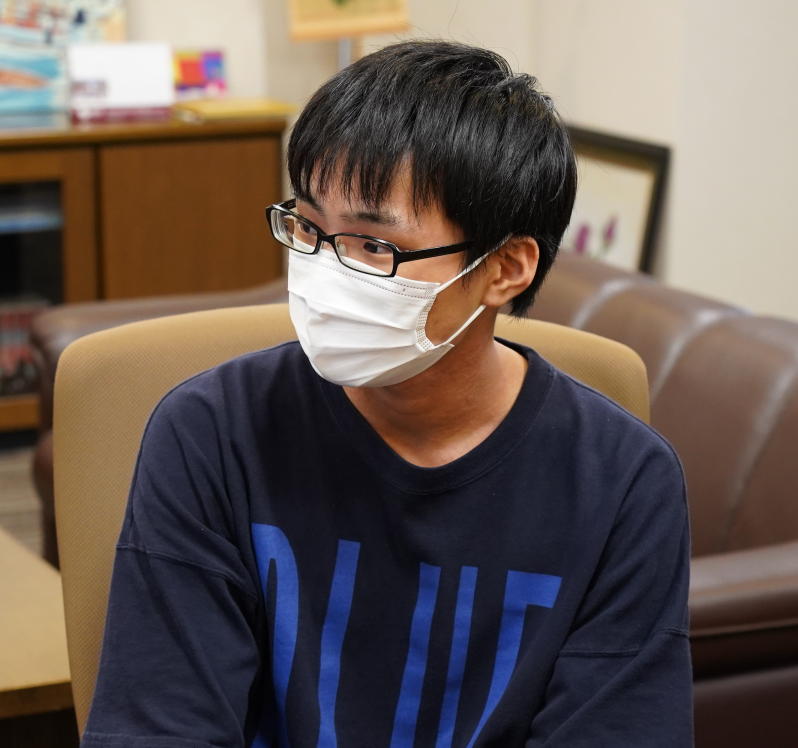 稲岡さん 私は中学時代から株式投資に興味があり、高校に入り投資の勉強を開始しました。その中で、実際の株式運用に機械学習、人工知能が用いられるなど、理工学の技術が投資と強く結び着いていることを知りました。このとき、理系選択だった自分の視野の中に、社会科学系の学部への進学が選択肢として入ってきました。
稲岡さん 私は中学時代から株式投資に興味があり、高校に入り投資の勉強を開始しました。その中で、実際の株式運用に機械学習、人工知能が用いられるなど、理工学の技術が投資と強く結び着いていることを知りました。このとき、理系選択だった自分の視野の中に、社会科学系の学部への進学が選択肢として入ってきました。その後、株式投資から企業経営におけるデータサイエンスに関心が広がり、企業経営とデータサイエンスの両方を学べる経営学部DSEPを志望しました。
鶴見 ありがとうございました。ちなみに、おふたりとも高校時代は理系選択だった、とのことですが他の経営学部DSEPのメンバーはどうでしょうか?
廣田さん DSEP全員の高校時代の文理選択は分からないのですが、私が知っている範囲のメンバーで言えば、全員理系選択だったようです。
経営学部DSEPに入ってみての感想
鶴見 実際に経営学部DSEPに入ってみてどうでしょうか?廣田さん データサイエンスの知識・スキルを学び、使いこなせるか・・・入学時は不安でした。しかし、自分から進んで学習した結果、着実に成長していると実感し、充実しています。
鶴見 どんな時に成長を感じますか?
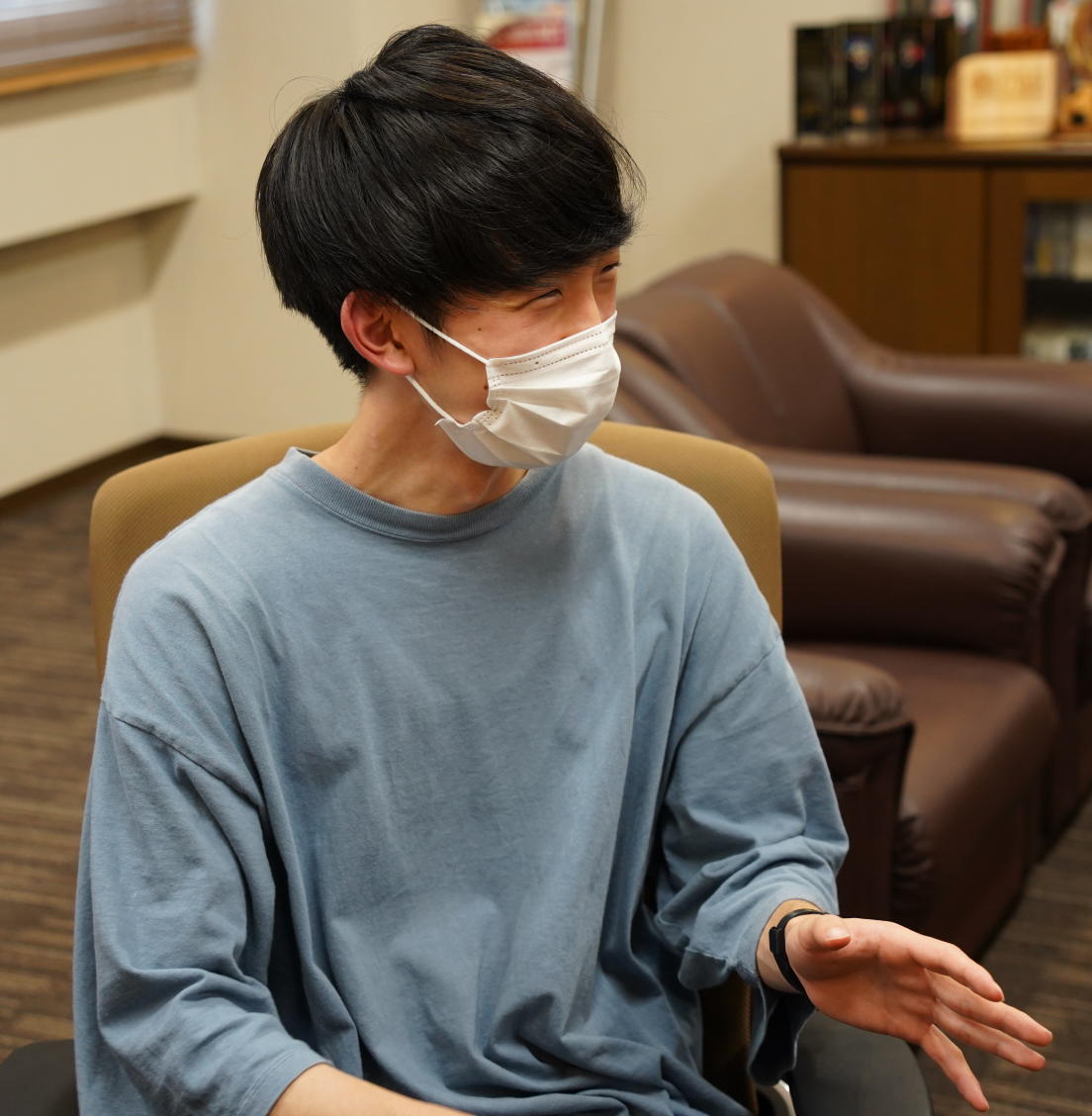 廣田さん 与えられたデータから結論を求める際、想定される結果、結論から逆算をして計画し、試行錯誤しながら、その通りにうまく結果が出た時、達成感、充実感を覚えます。
廣田さん 与えられたデータから結論を求める際、想定される結果、結論から逆算をして計画し、試行錯誤しながら、その通りにうまく結果が出た時、達成感、充実感を覚えます。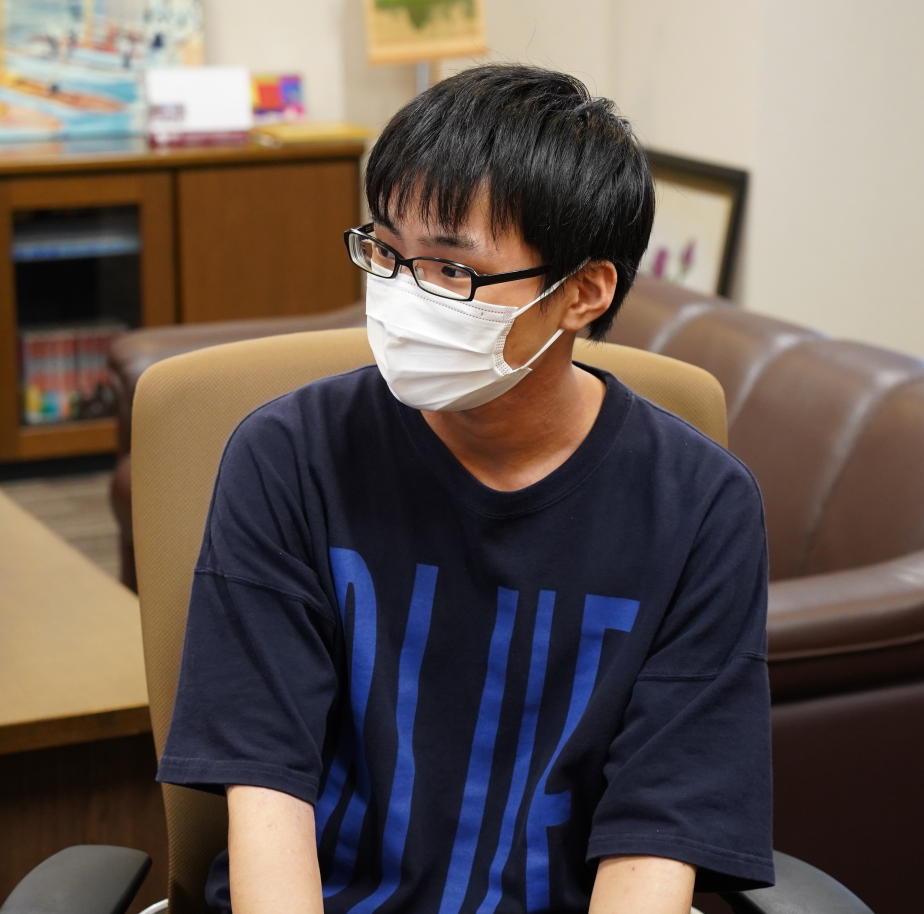 稲岡さん 視野が広がったと感じた時です。またDSEPに入って驚いたのが、12名という少人数制のため教授達との距離が近いこと。私たちの分析結果や研究報告について色々なフィードバックが聞ける点が、大変刺激的です。
稲岡さん 視野が広がったと感じた時です。またDSEPに入って驚いたのが、12名という少人数制のため教授達との距離が近いこと。私たちの分析結果や研究報告について色々なフィードバックが聞ける点が、大変刺激的です。データサイエンス・ゼミナールでの2教員指導体制について
鶴見 データサイエンス・ゼミナールでは約10名のDSEP生を2人の教員が指導します。今年は寺本先生(消費者行動論などの科目をご担当)、伊藤先生(統計学、ファイナンシャルリスクマネジメントなどの科目をご担当)による指導が行われています。このような2教員指導体制については、どの様な感想をお持ちでしょうか?廣田さん ゼミナールで取り組んだ分析に対する先生方のフィードバックから、マーケティング視点と統計分析視点との違いを学ぶときがあります。同じ、経営学の中で違う視点があるのは、とても興味深いです。
稲岡さん 異なる分野の教授2人の知見に1年生の時から触れられる環境は、恵まれており、意義深いと感じます。

春学期のデータサイエンス・ゼミナールでの活動について
鶴見 現在、データサイエンス・ゼミナールでは野村総合研究所「マーケティング分析コンテスト2021」に参加しています**。春学期は、コンペに向けた事前演習を中心に行ったと聞きました。どのように演習に取り組んだか?教えて頂けますか?
**マーケティング分析コンテスト2021 https://www.is.nri.co.jp/contest/
廣田さん 事前演習は、投資家に関するデータをどのようにビジネスに生かすか?という課題でした。色々と分析にチャレンジし、分かったこともあったのですが・・・私としては、大したことは分からずに終わってしまったと思っています。
鶴見 そうでしたか。うまく着地ができなかったようですが・・・分析手法は何を使いましたか?
廣田さん 分析手法としてはクラスター分析(似た性質のデータを分類する分析手法)、因子分析(データに背後にある共通因子を探り出す分析手法)に挑戦しました。
鶴見 分析手法については、先生方が「これを使いなさい」といった指導があったのでしょうか?また分析手法はどの様に学びましたか?
稲岡さん いえ、先生達はあくまで課題を提示されるのみで、事前の手法提示などはありません。分析のプロセスをどう組み立てるかに関しては、私たち学生自身で模索してゆく必要があります。そして、私たちが課題に取り組んだプロセスや結果に対して、教授達によるフィードバックが与えられる形で、ゼミは進みます。
分析手法は自分たちの考えや教授達のフィードバックを踏まえて、ネットや書籍から探し、選択しました。手法の理論的な内容や、分析に使用したRコマンダーやEZRなどのソフトウェアの選定、操作方法も自力で探しました。
結果、実践を前提とした分析手法の学びにより、理解も深まりました。また、必要な知識やスキルを自力で探す力も身に付いたように思います。
鶴見 ゼミのプロセスは、データサイエンティスト達が課題に取り組むプロセスそのものですね。教えてもらうのを待つのではなく、自力で必要な知識やスキルを探し、身に付け、可能性を自らの手で広げる力は、技術の進化スピードが速くなっている現代において大変重要な力だと思います。

ゼミを通じて発見した自分達の課題ついて
鶴見 データサイエンス・ゼミナールを通じて発見した自分達の課題があれば教えて下さい。廣田さん 発表の際のフィードバックで、教授達から、前提や条件を満たせていない、という指摘を度々受けました。課題の背景にある前提や条件を分析に反映すべきところを、見誤っていました。経営上の課題を的確に理解し、その内容をデータ分析にどう対応させるか?が今の課題のひとつです。
稲岡さん 使える分析手法が限られている点です。現象を説明するためのツールが少ないのは、大変不利です。使える手法を増やしてゆくのが今の課題です。
また手法や結果を説明する力も不足しています。春学期を通じて、特にデータ分析で「なぜ、その手法を選んだのか」と問われた時に回答に説得力が足りず、歯痒さを感じることが多かったです。1つ1つの手法や結果を分かり易く、適切に説明する力も高めてゆく必要があります。
鶴見 みなさんが、着実に力を身に付けつつあること。そして、その陰には、人知れず積み重ねた努力や苦労があることがよく分かりました。ありがとうございました。
現役DSEP生から高校生、受験生へのメッセージ
鶴見 さてインタビューの最後に、高校生、受験生に向け経営学部DSEPの魅力やメッセージをお願いします。廣田さん データサイエンスという学問は、これからどう社会が転んでも必要な学問です。
このデータサイエンスを用いる業界で、ビジネスをリードしていく存在はとても有意義であると考えています。少しでもそのような将来像を思い描いているのであれば、経営学部DSEPはとても有力な選択肢の1つだと思います。
そして、経営学部DSEPに入ろうとしている方に、もしデータサイエンスの知識がなくても、入学してから知識を身につけ、経験を積むことによって対処できると思います。現状に言い訳せず、自分の信念を貫いて入学先を決めてほしいと思います。
稲岡さん 最近では、データサイエンティストの需要が増えている、とよく聞くと思います。データサイエンスに直接携わる仕事でなくても、データ分析を必要とするような職業はますます増えると思います。さらに今後は、ビジネスとデータサイエンスの橋渡しをするような人材も必要になると思います。
そのような将来に興味があるという方は、ぜひ経営学部DSEPを目指してみて下さい。

鶴見 本日は、ありがとうございました。
稲岡さん、廣田さん こちらこそ、ありがとうございました。
---インタビューを終えて。
データサイエンスのスキルとプロジェクトを推進する力。その双方が若きDSEP生達に備わりつつあることを感じ、大変頼もしく思いました。この調子で成長できれば、将来、DSEP生達が大きく羽ばたくであろうことを期待させるインタビューでした。
なお、私が2人以上の先生から指導を受けたのは、大学院に入学してからで、それも修士課程2年の後半からでした。大学の学部1年から、少人数ゼミでその様な2名体制での指導を受けられるのを、正直うらやましく思いながらインタビューをしていました(自分たちでカリキュラムを構築しておきながら、こう言うことを思うのは大変おかしいかも分かりませんが・・・これが偽らざる本音です)。この教育は他の大学でも、なかなか体験することができないものです。この様な教育体験を経験してみたい、という方は是非経営学部DSEPへの志願をご検討下さい!常盤台で皆さんをお待ちしております!
横浜国立大学 経営学部 DSEP運営委員長
鶴見裕之
鶴見裕之